
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定して夫婦間の婚姻費用分担義務を定めており、この規定は、夫婦が別居中であったとしても婚姻関係を解消するまでの間において妥当します。そのため、夫婦は、その婚姻関係を解消するまで、互いの生活を助け合わなければならない法律上の義務あり、夫婦の中で収入の多い者から収入の少ない者へ生活費として婚姻費用を渡す義務があります。
分担を求めることができる婚姻費用の額は、夫婦それぞれの収入額や、どちらが子どもを育てているか、育てている子どもの人数等を考慮して決められます。
実務上は計算の目安となる「算定表」が公表されており(標準算定方式・判例タイムズ1111号285頁以下参照)、家庭裁判所ではこの算定表に従って婚姻費用の額が定められることが一般的です(算定表の表10~19の婚姻費用をご確認ください)。
(詳細はこちら⇒養育費・婚姻費用算定表)
婚姻費用の支払義務は、「生活保持義務」(=支払義務者が自身の生活を保持するのと同程度の生活を権利者に保持させる義務)と言われております。
そのため、別居後に婚姻費用として生活費を請求する場合は、まずは算定表を確認し、自身の請求額が妥当な金額の範囲か、ご確認いただけるとよいかと存じます。あらかじめ弁護士にご相談いただければ、より正確な金額をアドバイス差し上げることができますので、ご相談願います。
※正確な婚姻費用の額を確認されたい場合には、夫婦双方の収入を示すもの(最新の源泉徴収票や所得課税証明書等)をご相談時に持参願います。
算定表を用いて一例を見てみます。
・婚姻費用を支払う側(義務者):給与収入(会社員)/年収600万円
・婚姻費用をもらう側(権利者):給与収入(パート)/年収100万円
上記ケースですと、子どもがいずれも14歳以下ですので、
婚姻費用は婚姻生活を営むために要する費用ですので、本来は、婚姻費用が必要となった時期に支払がなされる必要があります。そうすると、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったとき、通常は別居時に婚姻費用が生じると考えることになります。
この考え方によると、義務者は、別居後何年も経ってから過去の婚姻費用をまとめて請求されるという場合が生じますが、義務者は婚姻費用の請求を受けることで初めて他方が扶養を要する状態になっていることを知ることも少なくなく、このような場合に扶養を要する状態以降の婚姻費用を全部支払わなければならないとすると、いささか酷とも考えられます。
そこで、実務上では、義務者が任意の支払いに応じない場合には、権利者が請求したとき(通常は婚姻費用分担調停等の申立時)に義務者の支払義務が生じるとすることが多いです。
そのため、婚姻費用の請求を検討されている場合は、速やかに婚姻費用の調停を申し立てることが肝要です。
事前に弁護士にご相談いただければ調停申立書の作成の具体的アドバイスを行いますし、ご依頼いただければ、弁護士において申立書の作成・提出を行います。
婚姻費用は、婚姻関係を解消するまでご自身と子どもたちの生活を守る大事な費用です。やむなく別居に至った場合は、できるだけ早く、勇気を出して、相手にきちんと婚姻費用を請求しましょう。ご自身での請求や調停申立てが難しいのであれば、弁護士にご依頼ください。適切にサポートいたします。
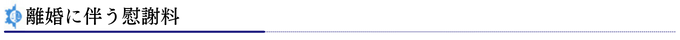
慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、1000万円を超える金額やこれに近い金額になることはほぼありません。離婚原因となった事情にもよりますが、不貞のケースでは、100万円から300万円の範囲におさまる場合が多いようです。

財産分与の対象となる財産は、婚姻してから夫婦が共同で築き上げた財産です。「共同で築き上げた財産」かどうかは、実質的に判断されます。
たとえば、形式的には財産の名義がどちらか一方になっていても、双方の収入で取得したものであれば財産分与の対象となりますし、一方の収入のみで取得した場合であっても、実質的には夫婦が共同で築き上げた(夫婦の一方が家事や育児をこなし、そのおかげで他方が働きに出て収入を得ることができた場合など)といえる場合には、財産分与の対象となります。
これに対し、夫婦の一方が親から相続した財産や、婚姻前から所有していた財産は、財産分与の対象にはなりません。これらは固有の財産として、原則として財産分与の対象から除外されます(特有財産と言います)。ただし、特有財産であっても、婚姻後に夫婦が協力したことで、特有財産の価値が維持された(散逸を免れた)と認められる場合や特有財産の価値が増加したといった事情が認められる場合には、その貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる余地もあります。
分与の割合は2分の1が基本ですが、財産に対する寄与度(財産の形成・維持にどのくらい貢献したか)も考慮して分与の割合を決めることになります。専業主婦であっても、家事労働により財産の形成・維持に貢献したと評価されるのが一般的ですので、財産分与を受けることができます。
財産分与の内容は、当事者間で話し合って決めることが可能ですが、分与の対象となる財産の範囲に争いがある場合や、住宅ローン付不動産がある場合には、当事者間で決めることが困難な場合もあります。







